皆さんは「耳マーク」を知っていますか?
これです。役所や図書館、病院などの公的機関で見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。

この「耳マーク」は、昭和50年(1975年)に名古屋で誕生しました。
全日本難聴者・中途失聴者連合会(全難聴)を中心に、聞こえに関する理解を広めるための普及・啓発活動が続けられています。
現在では、「聞こえない」「聞こえにくい」ということを周囲に伝え、理解や配慮を得やすくするための全国共通の公認マークとして広く使われています。
耳マークの由来と意味
耳マークの詳しい歴史については、全日本難聴者・中途失聴者連合会の公式サイトに紹介されています。
全日本難聴者・中途失聴者連合会(耳マークについて)
マークの上下には、
「聞こえにくいです」
「耳が不自由です」
「耳の不自由な方は筆談しますのでお申し出ください」
といったメッセージが添えられている場合もあります。
街中で見かけたときは、ぜひ注目して見てみてくださいね。
耳マークグッズもたくさん!
耳マークの普及を目的に、さまざまな関連グッズも販売されています。
ステッカー、バッジ、キーホルダーなど、日常の中で使いやすいアイテムが多くあります。
購入を希望される方は、お住まいの地域の全難聴加盟団体のホームページなどで確認・お問い合わせください。
以下の協会では、オンラインで耳マークグッズを購入することも可能です。
- 特定非営利活動法人 東京都中途失聴・難聴者協会
- 特定非営利活動法人 千葉県中途失聴・難聴者協会
- 特定非営利活動法人 愛知県難聴・中途失聴者協会
また、ネットショップなどでも、「耳マーク」とは異なるデザインで難聴を伝えるための商品が販売されています。参考にしてみてください。
私が使ってみた「耳マークシール」
私が持っているのは、耳マークのシールタイプです。
先日、診察券に貼って初めてクリニックに行ってみました。
「何も言わなくても気づいて、少しでも配慮してもらえるかな…」
そんな期待とドキドキを感じながら受付に出してみました。
最初の「今日はどうされましたか?」という問いかけは、スタッフの方が近くまで来て話しかけてくれました。
ただ、他の患者さんにも同じように対応されていたので、偶然かもしれません。
その後のやり取りでは特に変化はなく、結果的には“効果は?(笑)”という感じでした。
聞こえやすい・分かりやすい環境のために
クリニックや薬局では、名前や番号で呼ばれることが多いですよね。
診察の呼び出しは番号でも、会計時には名前で呼ばれることが少なくありません。
特に耳鼻科では、聞こえにくい方も多く利用しているはずです。
聞こえる・聞こえにくいに関係なく、誰にとっても「見て分かる」「聞いて分かる」仕組みづくりが大切だと改めて感じました。
耳マークは、そんなやさしい社会をつくる第一歩なのかもしれませんね。

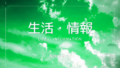
コメント