前回び続き、耳マークのお話です。前回の記事では、「耳マーク」についてその意味や活用の場面を紹介しました。私自身がもっている、「耳マークシール」の活用法を考える中で、「もし貼るならマイナンバーカードが一番便利なのでは?」と思ったのです。
役所の窓口で感じた“聞き取りにくさ”
役所の手続きは、どうしても大切な個人情報を扱う場面が多いですよね。
ですが、新型コロナウイルスの感染対策が続いていた時期から、今でも多くの窓口ではアクリル板やビニールカーテンが設置され、職員の方もマスクを着用しています。
そのため、声がこもって聞き取りづらかったり、大切な説明を聞き逃してしまったりすることがあるのです。
そんなとき、「最初から耳マークが貼ってあれば、お互いに安心してやり取りできるのでは?」と感じました。
相手に一目で「聞こえに配慮が必要なんだ」と伝われば、声の大きさや話し方を含めたコミュニケーションを自然に調整してもらえると思ったからからです。
マイナンバーカードに貼ってもいいの?
そう思い、念のためカードの更新時に役所の職員さんへ尋ねてみました。
すると返ってきた答えは「マイナンバーカードへのシール貼付は、あまりおすすめしません」とのこと。
理由を聞くと、「コンビニで証明書を発行する際、カードを機械に挿入するタイプの端末では、シールが引っかかる可能性がある」との説明でした。
確かに、カードの挿入口に貼りものがあると、トラブルが起こる心配がありますよね。
ただし、役所の窓口で使用する場合は「磁気部分が隠れていなければ問題ない」とも教えてもらいました。
カードは磁気部分をスライドさせて情報を読み取る仕組みとのことです。
実際のコンビニ端末は“置くだけ”だった!
ここでふと疑問が浮かびました。
「コンビニでの証明書印刷サービスって、本当に“挿入式”なんだろうか?」と。
気になって、主要なコンビニでのマイナンバーカード対応方法を調べてみたところ、結果は次の通りでした。
| コンビニ | 読み取り方法 |
|---|---|
| セブンイレブン | 置き型ICカードリーダー |
| ファミリーマート | 置き型ICカードリーダー |
| ローソン | 置き型ICカードリーダー |
| ナチュラルローソン | 置き型ICカードリーダー |
| ミニストップ | 置き型ICカードリーダー |
調べてみると、すべて「置き型」タイプ。
つまり、カードを差し込むのではなく、所定の場所に“置くだけ”で読み取る仕組みです。
役所の方が心配していたような「挿入口に引っかかる」トラブルは、実際には起きにくいということですね。
マイナ保険証でも問題なし
マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」も同様です。
医療機関でも置き型リーダーを使用しているため、耳マークシールを貼っていても支障はなさそうです。
もちろん、今後マイナンバーカードに紐づけられる情報が増えるにつれて、読み取りの方法や機器が変わる可能性はあります。
しかし、現時点では耳マークシールを貼っていても問題なく使えるケースが多いと感じました。
最後に
行政の手続きはどれも大切なものですが、聞き取りづらい状況では不安になることもあります。だからこそ、「伝わらない」「聞き取れない」といった小さなすれ違いを減らす工夫はとても大切だと感じました。
耳マークシールは、そうしたときに“お互いが気づきやすくなる”ための小さなサポートです。
まだ実際に役所で使う機会はありませんが、これからも「自分から分かりやすく伝える工夫」として、耳マークシールを活用していきたいと思います。

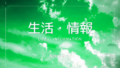

コメント